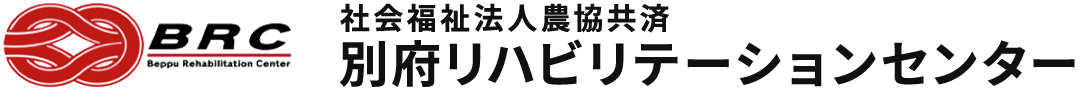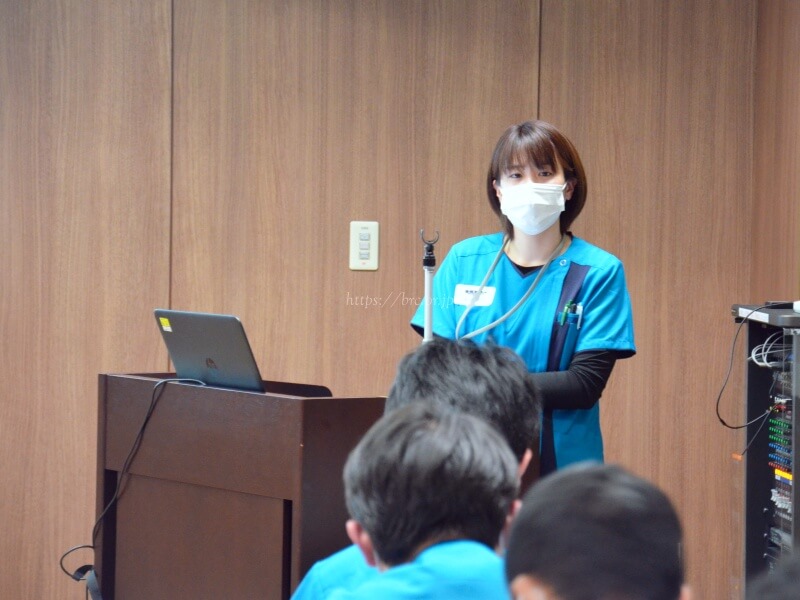5月12日 (ナイチンゲールの誕生日)は看護の日です。
5月11日から17日の「看護週間」の事業として、東部保健所が主体となり別府地区で多くの医療施設が参加し、それぞれの施設でふれあい看護体験を実施しました。

別府リハでも5月20日と21日に杵築高校から4名、別府鶴見丘高校から4名の学生をお迎えしました。

体験内容は、血圧測定や患者体験、防護具の装着体験、そして実際に患者さまとのふれあいなどをおこないました。

また、将来、医療職を目指すきっかけになればという思いから、希望者には薬剤師や診療放射線技師(レントゲン技師)からのお話も聞いていただきました。

今回の体験を通して、看護師の仕事を身近に感じ、少しでも関心を持ち、将来、看護師をはじめとする医療の道を目指すきっかけになれば、大変うれしく思います。
患者さまと職員との交流を図り、お正月ならではの遊びを通して新年を迎えたことを感じていただくため、1月8日にお正月会を開催しました。

がんばってカルタを取ります!
患者さま・職員全員で大カルタ取りや風船飛ばし、ダルマ運びをして盛り上がりました。

風船飛ばしでは、うちわが破れるハプニング!
患者さまの普段とは違う表情や隠れた身体能力が引き出される、特別な時間となりました。

みんなで協力してダルマを転がします

最後の一つが難しい!風船が飛んでいくと歓声があがりました

一生懸命にカルタを探している様子が伝わってきます!
職員は、患者さまの喜ぶ姿を想像しながら準備をおこないました。
今後も患者のみなさまに楽しんでいただけるよう、様々な行事を企画していきたいと思います。

最後にみんなで「三百六十五歩のマーチ」を歌いました
回復期リハビリテーション病棟では、先日認知症リハ・ケアワーキンググループ主催の勉強会をおこないました。
この勉強会は、スタッフが身体拘束を体験し、患者さまの気持ちを改めて考える機会になればと毎年開催しています。

スタッフが実際に身体拘束を体験し、ベッド上でのミトン・上肢抑制・胴抑制をしていきます。
体験したスタッフからは、「体が痛く大変だということがわかった」、「体だけでなく心の自由まで奪われているようだ」という意見が出ました。

ミトン・上肢抑制・胴抑制をしていきます
次に車椅子上での身体拘束を体験しました。
「背中の圧が長時間になるときつい」「すべてをあきらめる心境になる」といった意見もあり、改めて大切なことに気が付いた勉強会となりました。

車椅子での身体拘束体験です。圧迫感があり、窮屈な状態です。
回復期リハビリテーション病棟では、これからも患者のみなさまにより良いリハビリテーション・ケアを提供できるよう励んでまいります。

ズラリと並ぶ先輩の前での発表は緊張しますがとても勉強になりました
別府リハの回復期リハビリテーション病棟の療法士が所属するリハビリテーション部ではこの時期、別府リハ1年目の職員(新卒者、既卒者ともに対象です)が、担当した方に対しておこなったリハビリテーションをふりかえり、その中で感じた気づきや疑問を先輩療法士にぶつける「1年目職員事例検討会」を毎年おこなっています。
今年度は4名の1年目療法士(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が発表をおこないました。
別府リハでは「365日リハビリテーション」をおこなっていることから、1年目療法士の担当する方のリハビリテーションを先輩療法士が担当する日もあり、現在進行形でリハビリテーションをおこなっているときにも、先輩の指導を受けたり質問をしたりしやすい環境です。
しかし、時間をおいてあらためて論理的に整理すると、リアルタイムではきづかなかった疑問が湧いてくることはよくあること。
検討会本番では、作成した資料や電子カルテをつかって、退院までのリハビリテーションの経過を報告するとともに、今回整理するなかであらためて生じた疑問を述べました。
それぞれの発表後におこなわれる質疑応答では、先輩療法士から、厳しくも愛ある多くの質問やアドバイスが。
ひとりの先輩がコメントすると、さらにそれを受けてアドバイスをくれる先輩もいて、ディスカッションの場はどんどんあたたまっていきました。
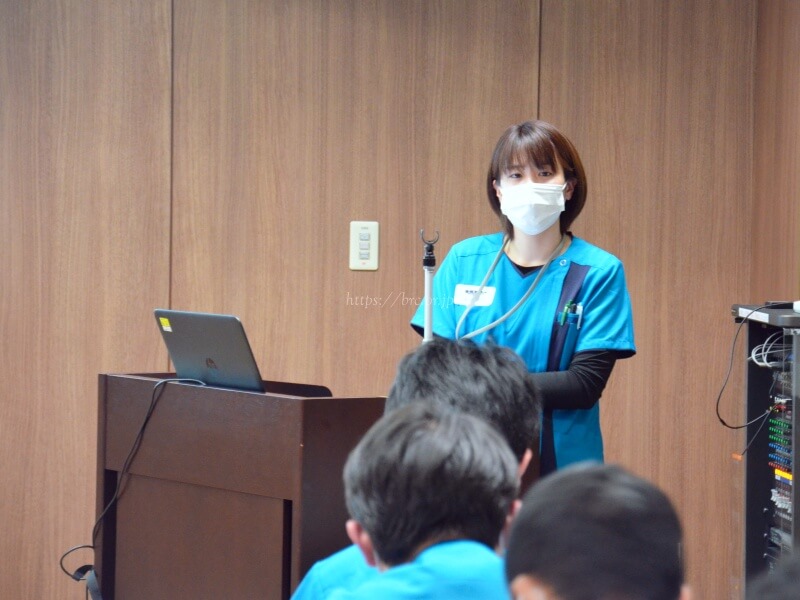
質問の意図を正しくとらえて適切に答えることも発表では大切です
1年目療法士が先輩たちの質問に答える姿はじつに堂々としていて、アドバイスをする先輩や上司も、彼らの成長をとてもたのもしく感じました。
発表を終えたひとりは「同じ職種の先輩からの助言はもちろんですが、今回はほかの職種の先輩からも質問やアドバイスをいただくことができ、異なる視点からのご意見は、とても勉強になりました」と話していました。
また、彼らの発表を準備段階からサポートした先輩療法士からは「入院中にも症状の評価やリハビリテーションの内容について相談にのっていましたが、退院後あらためて一緒にふりかえると、より一層、リハビリテーションを受ける患者のみなさまの視点で考えることができました」といった感想が聞かれ、先輩たちにとっても良い学びの場となったようでした。
別府リハでは、職員が安心して成長できる職場づくりをこれからもおこなっていきます。

別府リハの回復期リハビリテーション病棟では、新人教育の一環として、新人理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、自分の担当した方に対しておこなったリハビリテーションをふり返るとともに、そのなかで生じた疑問を先輩セラピストにぶつける「新人事例検討会」を開催しています。
この検討会では、スライドや抄録など、学会のようなプレゼンテーション資料を作らずに、日頃使用する「電子カルテ」にあるデータを使って説明をおこなうことで、研究の練習をするのではなく、毎日の臨床の力や考え方を育てることをめざしています。
しかし、こういったスタイルでおこなうはじめての検討会は、どうやってふり返っていけばよいのか、どのようにすれば聴いてくれる人に伝わるのかなど、新人にとっては難しいことだらけです。
そこで今年度から、準備を始める1年目職員に対して、先輩たちが「こうやって発表するんだよ」とお手本を示す機会を作ることにしました。

模範プレゼンテーションをおこなってくれたのは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士それぞれの先輩。
先輩たちはスクリーンに映した電子カルテを上手に使って、脳画像や、リハビリテーションの目標、介入方法、経過などをわかりやすく説明してくれました。

ひとつのプレゼンテーションが終わるごとに時間をとった質疑応答では、1年目の職員以外にも手を挙げる職員が多く、たくさんの質問や意見、アドバイスが出て、和気あいあいとした雰囲気の中、有意義な時間となりました。

前方の席でプレゼンテーションをしっかり見た新人職員からは、
「先輩たちが日ごろどのようなことを考えてリハビリをしているのか、知ることができました」
「どんな風に発表するのか、発表の流れを理解することができました。」
「抄録やスライドを使わないで発表する形式を初めて見て、自分で発表するイメージが湧きました」
などの感想が聞かれました。
別府リハでは、今後も新人職員が安心して成長できる環境を整えていきます!